|
俺がこの町に引っ越してきたのは、だいたい1年前のことだ。 転勤を言い渡された土地がここ、アクアスだった。 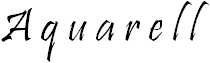 この町は小さい。 といっても周りの街に比べれば、の話だけど。 一応観光都市とはされているけど、こんな小さな町なんて半日あれば一回りできる。 有名な行事はあるけど、1年に1回だったり3年に1回だったりで、滅多に遭遇できない。 まぁ、ここを観光する人は、その景観と人との触れ合いを目的としているらしい。 確かに、この町の人はのんびりとしていて、お人好しが多かったりする。 だからなのか、配達に行くと、大抵何か出してくれる。 お茶だったり、お菓子だったり。 そして少しおしゃべりをする。 こんなのんびりとした仕事があっていいのか、と、この1年何度思っただろう。 「この町の空気がそうなんですよ。別にいいんじゃないですか?」 年下の同僚はそう言った。 今ではそれが普通のことになりつつある。 前の仕事先では有り得なかったことだった。 絶対に乱雑に扱わないこと。 出来るだけ手渡しすること。 送り主が込めた想いも一緒に届けること。 それが今の事業所で初めに言われたことだ。 同僚は、所長がロマンチストなんですよ、と言っていたけれど、実は俺は感動していた。 手紙には色がある。 込められた想いが色の付いた霞のようにその封書を包んでいる。 俺にはそれが見える。 この星の人間は大抵ちょっとした力を持っていて、俺の力は物に込められた色を見るというものだった。 配達する時、手渡す時、俺はそれがこぼれないようにそっと扱う。 手紙を届け主に手渡すと、その霞は霧散して届け主に降り注ぐ。 すると、内容にもよるけれど、大抵の場合、その人は笑顔になるのだ。 色によっては、その場で泣き出してしまう人もいる。そういう時は落ち着くまで傍にいる。 ここに来て、そんな配達をして、初めてこの仕事を魅力的に感じたのだ。 だから未だに辞められない。 母星とは大きさが違うから、この星は1年が16ヶ月ある。 そこで9月というと、夏から秋になる、ちょうど季節の変わり目に当たる。 少しずつ日が短くなっていくのを感じながら、事業所を出た。 「太一君!」 のんびりと石畳を歩いていると、背後から名前を呼ばれた。 「お、ニノ。お前も上がり?」 「うん。ちょうど太一君の背中が見えたから」 走ってみました、と同僚の二宮が笑った。 そして2人で歩き出す。 同じアパートに住んでいるから帰り道は同じだった。 「日も短くなってきたなぁ」 「そりゃそうですよ。明日は星祭りですもん」 「は?星祭り?」 ニノの口にした単語は聞き慣れないものだった。 「あれ?太一君知らない?」 「知らない」 「ここじゃ有名なんですけどねぇ」 そう言って二宮は首を傾げたが、すぐにあぁ、と声を上げた。 「去年は太一君が赴任してくる1週間前にやったんだ」 そうだそうだと一人頷く。 「毎年開催日が違うんだ?」 「うん。祭りっていっても夜店が出る訳じゃないんですけどね。みんなで一斉に電気消して星を眺めるんです。だから星が一番キレイに見える日が星祭りの日」 「雨降ったらどうすんだよ」 「降りませんよ。相葉ちゃんがいるから」 「あぁ、そっか」 言われてみれば、二宮の同居人の相葉は風民(しなとべ)だった。 正しくは気象管理局局員だけど、誰もそんなふうには呼ばない。 風を起こして雲の動きを管理して、気象を管理してる。だから『風の民』。 もともとこの星は人間の住むことの出来なかった星だから、人工的に環境を変えた当時は天気が不安定で、 それを制御するために作られた役職らしい。今は天気予報とか嵐の制御とかを仕事にしている。 「明日の夕方まで抜けれないらしいですよ、あのヒト」 昨日文句言ってました、と二宮は笑う。 その様子を想像して、俺も思わず笑った。 「じゃあ、また明日」 「おやすみなさい」 アパートの真ん中にあるホールで、二宮は向かって左側の階段を上っていった。 それを見送って、俺は右側の階段を上る。 自分の部屋は3階だけれど、2階の一番手前の部屋のインターホンを鳴らした。 「はいはい」 ガチャリと音がして、扉が開く。 「あ、太一君、お帰り」 そう笑って、部屋の主は俺を出迎えた。 「ただいま。今日何?」 「チキンのトマト煮だよ。まだ完成してないけど」 苦笑を浮かべて、松岡は俺を部屋に招き入れてくれた。 このところ面倒くさくて、ほぼ毎日松岡に夕飯を作ってもらっているのだ。 「今日長瀬いないんだ」 通されたリビングで、いつものようにソファに荷物を投げて、いつもそこに陣取っている奴の姿がないことに気付いた。 「タクシー仲間と飲み会だって」 俺の言葉に松岡が台所から答える。 「あいついないと静かだなぁ」 そう呟いて、俺はソファに倒れ込むように座った。 長瀬は二輪タクシーの運転手をしている。 水路が張り巡らされて、細い道ばかりのこの町では四輪の自動車は乗り回せない。 だからバイクの後ろに客席を繋げた二輪タクシーが観光者の足になっている。 昔、母星から観光に来て、長瀬は二輪タクシーに惚れ込んだらしい。 この町への母星からの移住者は多くないのに、大した物好きだ。 「太一君は明日休み?」 薄紫のエプロンをしたまま、松岡がリビングに戻ってくる。 「いや、普通にあるけど」 「そっか。でもこの時間には帰ってくるんだよね?」 「残業の予定はないよ」 「ならいいや」 松岡はホッとしたような表情を浮かべた。 「星祭りってやつ?」 「えっ?あ、うん。それ。大抵の人は恋人と過ごすんだけど、ここの住人はみんなフリーでしょ」 みんなでご飯食べようかって企画してて、と苦笑する。 「俺らがめっちゃ寂しいやつらみたいじゃん」 俺も笑いながらそう告げると、松岡は、でもホントのことでしょ、と笑い返した。 「お、そろそろかな」 松岡は時計を見て台所に戻っていく。 鍋の蓋を開いたのだろう。トマトの良い香りが鼻に届いた。 今日は休みだという松岡に見送られて、アパートを出た。 「おはようございます」 ちょうど階段を降りてきた松本が声をかけてきた。 松本も二宮の同居人だ。 「出勤っすか?」 「はよっす。おう。稼がなきゃ」 俺が笑いながらそう答えると、松本も笑みを浮かべる。 「今晩、みんなでご飯食べるって聞きましたけど」 「あ、そっちまで誘ってたんだ」 「昨日智君が、茂君に誘われたって」 途中まで道は同じだから、2人で歩いていく。 「そっか、2人ともプーだもんな」 「ホントあのヒト達何してるんでしょうね」 松岡の正面の部屋に住む茂君も、松本の同居人の大野も、本人達は働いていると主張しているが、何をしているのかさっぱり分からない。 日がな一日家にいたりする。というか仕事に出かける様子を見たことがなかった。 でもお金に困っているようには見えないし、むしろあのアパートの中で一番金持ちなのはあの2人だろう。 「2人とも変人だから」 そう言うと、松本は、確かにと笑った。 2人が何をしていようが別に構わないから。 「じゃあ俺はこっちだから」 大通りに出て、松本と別れる。 「山口君によろしく」 「はい。じゃあまた夕方」 松本は手を振って、海の方に歩いていった。 松本は、山口君と同じ海洋管理局で働いている。 風民と同じく、そんな長い名前は滅多に呼ばれなくて、海守(わだつみ)と呼ばれてる。 サーファーが趣味と実益を兼ねて就くことが多い職業だ。 夜勤明けの山口君は、きっと波に乗ってから帰るんだろう。 「よし、俺も働かなきゃ」 今日もまた手紙を待ってる人がいるから。 「すごいね、太一君」 荷物の山を持って事業所に戻ると、二宮がニヤニヤしながらそう言った。 「モテモテじゃないですか」 「どこから情報が流れてるんだか・・・・・・・・・」 俺のぼやきに二宮は笑う。 「だって太一君人気者だもん。こないだ俺訊かれたし」 「お前かよ」 自分のデスクに貰ったプレゼントの山が出来た。 本人が忘れていたのに、配達先の馴染みの人達が、誕生日でしょう、といろんなモノをくれたのだ。 「おめでとうございます、太一君」 「あんまめでたい歳じゃないけど」 ありがとう、と告げると、少し嬉しそうに表情を緩める。 「ちなみに今はプレゼントはないですよ」 「ないのかよ」 「俺が倹約家なの知ってるでしょ〜」 「そういうのはケチって言うんだよ」 「そんな身も蓋もない言い方やめてください」 俺達のやりとりを聞いていた同僚達が笑い声を上げる。 「確かに二宮はケチだよな」 「お前に奢ってばっかりだよ、俺」 「だって年上を立てなきゃいけないでしょ」 背の高い奴に頭のてっぺんをぽんぽん叩かれ、二宮は文句を言った。 そのままウダウダとおしゃべりが続く。 前の職場ではこんなやりとりはなかったなぁと思いながら、その辺にあった紙袋を拝借した。 貰ったどの包みからも、柔らかく温かい色が溢れ出てる。 開けるのは家に帰ってからにしよう。 それぞれに込められた想いを想像して、心の中で小さく、ありがとうと呟いた。 今日は珍しく、いつもより30分早く終業のベルが鳴った。 「あれ?」 「星祭りの日は早く終われるんですよ」 首を捻る俺に、二宮がそう肩を叩く。 「そうなんだ」 「早く上がりましょ。所長も早く帰りたいみたいだし」 その言葉に窓際を見ると、いつもの如く忙しそうに、帰る準備をしていた。 「娘さんと約束してるんだって」 「へぇ。マイホームパパなんだなぁ」 俺は急いでデスクの上を片付ける。 そしてロッカールームに向かった。 「見事に雲一つねぇな」 「帰ったら相葉ちゃんを労わなきゃ」 俺の呟きに、二宮がそう笑う。 「すげぇな」 「命張ってますもんね」 風民は殉職率が高い職業でもある。自然と闘う役職だから仕方ないのかもしれないけど。 「そういえば、あれ何」 帰り道、ずっと気になっていたモノを指さして二宮に訊く。 それはどの家の扉の横にも設置されていた燭台のようなもの。 「ほら、星祭りは電気を全部消すって言ったじゃないですか。でも灯りないと何にも出来ないから、蝋燭は灯してもいいんですよ。だから」 「家の前にも?」 「う〜ん、何だったかなぁ?なんか理由があったと思うんだけど、覚えてないや」 二宮は首を捻り、そう苦笑する。 「消灯は6時半ですよ」 「日の入りと同時か」 「同時に蝋燭も点けます」 「蝋燭買ってないや」 「茂君とか、きっと買ってますよ」 「貰えばいっか」 どの家の前にも、小さな燭台が飾られている。 既に蝋燭を置いている人もいた。 少し沈みかけた夕日が白い家並みを金色に染め始める。 蝋燭が灯された町を想像して、久しぶりにワクワクした気持ちを味わった。 「おかえりぃ」 アパートの庭にはテーブルが設置されていて、着々と準備は進んでいるようだった。 「ただいま」 俺と二宮の姿を確認して微笑んだ茂君に、俺は笑い返す。 「着替えてきますね」 二宮はそう言ってアパートの方に歩いていく。 「松岡から聞いた?」 「みんなで飯食うんでしょ?聞いたよ」 「あ、そうや。蝋燭いくつか持ってき。燭台もこれあげるわ」 ふと思い出したように茂君は俺に黄銅製の小さな燭台を手渡して、蝋燭を袋に詰め始める。 「ありがと」 「火ぃ点けるだけにしとくとえぇで。火はある?」 「あー、ライターあったかな?煙草最近吸ってないから」 「なら僕の使い」 そしてライターも一緒にくれた。 「消灯までまだもうちょいあるから物の確認しといた方がえぇよ」 「大丈夫だよ。誰かさんみたくおっちょこちょいじゃないから」 「・・・・・・・・・僕のこと言っとる?」 「着替えてくるね」 わざと返答をせず、笑ってその場を離れた。 茂君はギムナジウムの先輩だった。 ギムナジウムはここからもっと西にあるクライツという大きな都市にあったから、 まさかこの町出身で大学出てから帰ってきてたなんて知らなかった。 赴任が決まってアパートを探してるときに出会って焦ったけれど。 言われたとおりに蝋燭の準備をして、簡単に部屋を片付けて外に出る。 日はもっと落ちていていた。 時計の針は6時を指していた。 消灯の時間は近い。 「あ、太一く〜ん」 でかい影が走り寄ってくる。 恐らく飛びついてくるだろうと予測して少し避けると、そのまま俺の後ろに突っ込んでいった。 「何で避けるんですか!」 「暑苦しいから」 非難の声を上げる長瀬に俺はそう笑って、食べ物が並び始めたテーブルに向かう。 料理の山盛り乗った大皿とビール瓶が山程乗っていた。 テーブルから少し距離を置いて、バーベキューコンロがある。 氷と水が入れられた大きなクーラーボックスにはいろいろな酒やジュースが冷やされて、封が開けられるのを待っていた。 「よ、主賓」 俺の姿に気付いて、既に飲み始めていた山口君が声を上げた。 「もう飲んでんの」 「待てっちゅーたんやけどねぇ」 大皿を持って茂君が現れる。 「だって夜勤明けだよ?自分にご褒美」 茂君の嫌味にも負けず、山口君はグラスに口を付けた。 「いつもやないかい」 そして叩かれた酔っ払いは、ブチブチ文句を言いながら姿を見せた松本達に酒を勧めだした。 「初、星祭りやね」 その姿を苦笑しながら見ていると、茂君がそう言った。 「うん。去年は俺が来る前に終わっちゃったんだって?」 「せやね。日は毎年変わるからな。風民が天気動かしてくれるから、出来るだけたくさんの星が見える日が選ばれるんよ」 「ふぅん。・・・・・・・・・・あ、そういえば、何で扉の前に蝋燭飾るの」 そう切り出して、ふとアパートの住人全員が揃っていたことに気付く。 二宮達5人と、茂君と山口君と、松岡、長瀬、そして俺。 「坂本君達、もうすぐ来るって」 松岡が電話片手にそう声を張り上げる。 「はいよー」 誰かがそう答えた。 「昔の話やね。この町があんま栄えてへん時な、病気が流行ったらしいねん」 茂君が、人数分のグラスにビールを注ぎながら話し始める。 「そん時は、ここは僻地やから。ほら、北にある2つの大橋無かったら、河に囲まれて、ここ、孤立してまうやんか。で、結構な数の人が亡くなったらしいねん」 ビールの注がれたグラスは、長瀬の手によって、全員に配られる。 「で、その時、たまたま旅人がこの町に辿りついてん。その人医学にも精通しとったらしくて、まぁ、後は想像できると思うけど」 「その人のお陰で町の人たちは助かった?」 「せやね」 その時、アパートの門の辺りに2人の影が現れた。 「わりぃ、遅れた」 「こんばんわー。もうすぐ消灯時間だよ」 大きな袋片手に現れた坂本君と長野君がそう言う。 言われてみればもうすでに日は暮れてしまっていた。 その言葉に二宮達が蝋燭に火をつけ始める。 時計を見るとあと2、3分だった。 「井ノ原は少し遅れるって」 そんな声が聞こえる。 「その旅人の偉いところは絶対にお礼を受け取らんかったことやねんな。 町の人がどんなに薦めても何も受け取ってくれへん。そこで町の人は考えた。 この旅人に素晴らしい景色をプレゼントしたらどうかってな。それで始まったんが星祭りや」 「ロマンチックー」 突然、長野君がテーブルの皿を退かし、坂本君が持ってきた袋の中に入っていた大きな箱を置いた。 「何?これ」 ちょうどその時、遠くの方から鐘の音が聞こえた。 同時に街灯が順番に消えていく。 蝋燭の炎が、ぼんやりと辺りを照らしている。 「太一、上、見てみ」 茂君の言葉に従って、俺は空を見上げた。 「・・・・・・・うわぁ・・・・・・・・・・・・」 そこに広がっていたのは、今にも落ちてきそうなくらいの星の海。 「蝋燭は、旅人がプレゼントの場所まで迷わないようにするために灯された」 「家の前に飾るのは、彼を歓迎し、感謝の意を持っていることを示すため」 坂本君と長野君の言葉に、視線を戻す。 「太一」 戻した視線の先。 テーブルの上では、大きなケーキに蝋燭が灯されていた。 「おめでとう」 気付けば、全員が俺を囲むように、テーブルの周りに立っていた。 「お前がこの町に来てくれて、一緒に暮らすことができて、嬉しいよ」 山口君がそう言って、全員がグラスを持ち上げた。 「旅人の話な。続きがあんねん」 茂君もグラスを掲げて、笑う。 「旅人は町民のプレゼントに感動して、そのまま永住したんやって」 「できれば、俺ら、もう少し太一君と一緒に過ごしたいなー、と思うんだけど」 「太一君はどうですか?」 茂君の言葉を、少し恥ずかしそうに松岡が引継ぎ、長瀬が締めた。 視線を廻らせると、全員が笑って俺を見ている。 そんな、 こんなことされたら、 仮令出て行くことを考えていたとしても。 「・・・・・・・まだ、いてやってもいいよ」 出て行きたくないなんて、言いたくないから、わざと、そう言った。 「ホントっすか!?」 俺の答えに長瀬が一番に嬉しそうな声を上げた。 「お、じゃあ太一の誕生日と永住宣言に乾杯しようぜ!!」 そして山口君がそう声を上げると、全員が笑いながらグラスをさらに高く掲げた。 「え!!?永住するとは言ってないんだけど!!!」 「どうでもいいって、そんなの!!飲もうぜ!!」 「どうでもいいのかよ!!」 初めの台詞では俺が主役のはずなのに、それがどうでもいいことになって、あっという間に宴会が始まった。 「ロマンチックの欠片もないし」 「しょうがないんじゃないですか」 俺の呟きに、横にいた大野がそう言った。 「ロマンチックだったら俺らじゃないですもん」 「・・・・・・・・そーだなー」 そして俺はグラスに注がれたビールに口を付けた。 昔話の旅人は、きっとプレゼントに感動しただけじゃなかったんだろう。 自分を迎え入れてくれた人々に感動して、一緒にいたいと思ったんだ。 もう原型が判らないくらい解体されたケーキからは、それでも穏やかな色が溢れ出していた。 Happy birthday, Taichi !! ---------------------------------------------------------------- 33歳おめでとうございます!! やー、まだまだ30歳には見えませんね! 今やいろんな局で引っ張り凧のアイドルになってますが、無理はせず、でも頑張ってくださいね。 これからもずっとアナタについていきます!! ダラダラした話が書きたかったので、この設定になりました。 分かる方には分かる設定ですねー。 久々の作文は楽しかったです(笑) よろしければお持ち帰りください。 改めまして、おめでとうございます!! 2007/09/02 c l o s e |